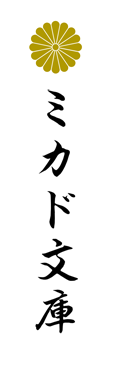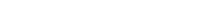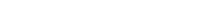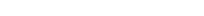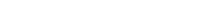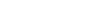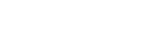海の日
「海の日」は、平成7年(1995)「国民の祝日」に制定された。「国民の祝日に関する法律」に「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」と定められている。当初は7月20日と定められたが、平成15年以降、7月の第3月曜日と改められている。今年(令和2年)は東京オリンピック・パラリンピックの予定日程を考慮して、特別に7月23日(木)へ移された(ただし、大会は来年に延期)。
この祝日は、戦前の「海の記念日」に由来する。明治9年(1876)、明治天皇(23歳)は、奥羽(東北地方)や函館へ巡幸の後、灯台巡視船「明治丸」に乗り還幸された。その際、海が荒れて難航したが、7月20日、御一行は無事に横浜港へ到着された。これに因んで、昭和16年(1931)より7月20日が「海の記念日」と定められていたのである。
海と関わりの深い日本では、「国民の祝日」として世界的に稀な「海の日」に関連した、各種の行事が催されている。
【コラム】「全国豊かな海づくり大会」への行幸啓
「全国豊かな海づくり大会」は、昭和56年(1981)、ハゼなど魚類の研究に熱心な上皇陛下が皇太子の時期に始められた。それ以来、妃殿下と共に行啓され、やがて御即位後も両陛下お揃いで御臨席を続けられてきた。それゆえ、昭和時代の全国植樹祭と国民体育大会への行幸啓と並び、「三大行幸啓」の一つとなったのである。
この大会は、全国都道府県の持ち回りにより開催される。川が海に通じているため、海に面していない内陸県(滋賀県・岐阜県・奈良県など)も開催地となった。両陛下は、大会前後に開催地周辺を御視察になり、大会当日、当該地に縁の深い魚や貝を放流される。
平成21年(2009)以降は、天皇陛下のご負担軽減のため、大会式典への御臨席のみとされてきたが、御代替わり直後の令和元年(2019)9月8日、秋田県秋田市の県立武道館で開催された際、天皇陛下は次のような「おことば」を賜わった(宮内庁HPより一部引用)。
四方を海に囲まれた我が国は、古くから豊かな海の恵みを受けてきました。また、山や森から河川や湖を経て海へ至る自然環境と、そこに育まれる生命や文化は、私たちに様々な恩恵をもたらしてくれます。
私自身、以前に鳥海山に登った折に、鳥海山の雪解け水がブナ林を養い育て、伏流水となって山麓の田畑を潤し、やがて日本海に注いで良質なイワガキを育んでいると聞き、山と海、そして人間との大切なつながりを感じたことを思い出します。
このような豊かな海の環境を保全するとともに、水産資源を保護・管理し、海の恵みと美しさを次世代に引き継いでいくことは、私たちに課せられた大切な使命であると考えます。
今年(令和2年)の大会は宮城県石巻市で開催される予定であったが、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、開催が見送られた。
【参考文献】(敬称略)
・徳仁親王著『水運史から世界の水へ』(NHK出版、平成31年)
・所功著『「国民の祝日」の由来がわかる小事典』(PHP研究所、平成15年)
・宮内庁HP「第39回全国豊かな海づくり大会」(「主な式典におけるおことば(令和元年)」)
(https://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/48#185)
・東京海洋大学HP「重要文化財明治丸」(https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/facilities/meijimaru.html)