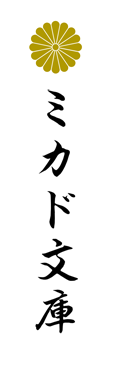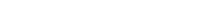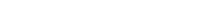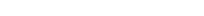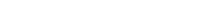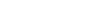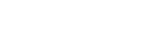鎌倉時代の両統送立と花園天皇の皇太子に対する御教訓
所 功
現存皇族の漸減と現行典範の改正
第126代の新天皇陛下が皇位を継承され、即位礼も大嘗祭も盛大厳粛に執り行われてから、はや4年を経て「令和」の御代はおおむね安泰のようにみえる。しかし、問題がない訳では無い。それどころか、かなり深刻な状況がほとんど改善されていない。
その最たる課題は、天皇陛下を成年皇族として輔佐し公務を分担されうる方々が既に少なく、いよいよ減少しつつある。とりわけ今上陛下の内廷皇女で健やかに成人された愛子内親王も、皇嗣として確定している秋篠宮殿下の次女佳子内親王も、現行法のままであれば一般男性との結婚により皇籍を離脱されるはかない。それによって お二方とも父君と母君を身近にお支えなさることができなくならざるをえない。
そこで、政府では昨年来、「皇室典範特例法の付帯決議に関する有識者会議」において検討を重ね、①皇族女子が結婚後も皇族として皇室に留まりうるようにすること、②戦後GHQ占領下で皇籍離脱を余儀なくされた旧宮家の男系男子孫を現存宮家の養嗣とすること、などを最終答申を受理し国会に報告している。しかし、1年近くたっても具体的な法改正の動きがみられない。。
そのため、次の次に皇位を受け継がれる秋篠宮家の長男悠仁親王(16歳)への期待と不安が、いよいよ大きくなっている。その期待とは、現行法のままでも男系男子の悠仁親王に継承されていくと見通せるからである。ただ、現行法のままならば悠仁親王の結婚相手は男子を儲けなければならない、という重圧が強くなるからである、しかも、より重要なことは、皇位継承者としての御心得をどのように学ばれるかであろう。この点、今回紹介する花園天皇の「太子を誡むる書」は、ご参考となるにちがいない。
大覚寺統と持明院統の交互擁立
いわゆる万世一系の皇統は、必ずしも親子で相承され得ないことがあった。とりわけ鎌倉中期、後嵯峨上皇が後継の君を特定せずに崩じられた。そこで、後深草上皇の院政とするか亀山天皇の親政とするかの決定を鎌倉幕府に委ねて以来、皇嗣の擁立に幕府の介入が慣例となったのである。
その結果、亀山天皇の後に立てられた後宇多天皇の系統(譲位後の御所にちなんで大覚寺統という)と、その次に立てられた伏見天皇の系統(譲位後の御所にちなみ持明院統という)との間で、相互に皇太子を立て即位せしめる両統迭立(てつりつ)という仲裁案が示された。それ以来の皇位継承は、ほぼこれに従わざるを得ないことになったのである。
すなわち、後伏見上皇の後は後二条天皇が立てられた。ついで、その皇太子をめぐり、後二条天皇は皇子の邦良親王を望まれ、後伏見上皇は父帝の意を承けて異母弟の富仁親王を推され、双方とも競って幕府に働きかけたが、幕府は両統迭立の方式により後者を支持している。
そして、延慶元年(1308)大覚寺統の後二条天皇が崩御されると、持明院統の皇太子富仁親王(11歳)が践祚して、花園天皇となられ、その皇太子には、九歳も年上ながら大覚寺統の尊治親王(20歳)が立てられた。ついで、文保2年(1318)、花園天皇の譲位により皇太子が後醍醐天皇として践祚されたときは、後二条天皇の遺志を汲んで、同じ大覚寺統の邦良親王を皇太子に立てられたのである。
けれども、その急逝により、持明院統の量仁親王を皇太子とされたところ、持明院統側から後醍醐天皇に譲位を迫る動きが強まった。それに対して親政をめざされる後醍醐天皇は、ひそかに討幕計画を企て、苦難の末、ついに「建武中興」を成就されるにいたった。
花園天皇の御日記と甥の皇太子への御訓戒
このような両統迭立の時期に、持明院統の天皇として11年、また上皇として30年、誠実に務めを果たされたのが、第95代の花園天皇である。その御在位中の前半は、父帝の伏見上皇が院政を敷かれ、御譲位後の大半も、大覚寺統の後醍醐天皇が親政を行われた。といえば、ほとんど御治績のない天皇のように思われるかもしれない。
しかし、必ずしもそうではない。否、むしろ極めて注目すべきものを残しておられる。それは、御幼少のころから建武2年(1335)御落飾のころまで30年近く御日記を書き綴られそのうち17年分47巻の御宸筆本が現存しており、また「誡太子書」や「学道之書」の御宸筆草稿なども伝存している(いずれも現在宮内庁書陵部蔵)。それらを通じて、花園天皇の深く鋭い御見識を拝することができる。その一端を紹介させていただこう(原文は漢文)。
まず御在位10年目の正和6年(1317)を文保元年と改元されて間もない4月、「誠に不徳の身、いかでか亀山院以後(大覚寺統)代々の聖代に軼(す)ぎんや。……ただ運の拙き、徳の薄きことを歎くべし。春宮(皇太子のち後醍醐天皇)は、和漢の才を兼ね、年歯父の如し。……朕は随分稽古し、学は至らずと雖も、心を励まし徳を勤(いそ)しみ仁を施さん」と記されている。これによれば関東(幕府)でも皇太子の尊治親王(30歳)を評価しているのは、大覚寺統の御歴代がすぐれておられ、また親王が和漢の学才を兼備されているからだと認め、省みて自らの不徳を歎き、学問に精進する決意を示しておられる。
また、御譲位13年目の元徳2年(1330)、その前年に、17歳で元服した甥の皇太子量仁親王(のち光厳天皇)に対して書き与えられた「太子を誡むる書」には、次のごとく記されている。
・愚人おもへらく、「吾が朝は皇胤一統し、彼の外国の徳を以て鼎を遷し勢に依りて鹿を逐ふに同じからず。故に徳微なりと雖も、隣国窺覦の危き無く、政乱ると雖も、異姓簒奪の恐れ無し……」と。……惟ふに、深く以て謬りと為す。もし主(天皇)賢聖に非ざれば、則ち唯だ乱数年の後に起らんことを恐る。……内に哲明の叡聡有り、外に通方の神策有るに非ざれば、則ち乱国に立つことを得ざらん。これ朕、しひて学を勧むる所以なり。……この弊風の代に当りて、詩・書・礼・楽に非ずんば得て治むべからず。是を以て寸陰を重んじ、夜を以て日に続ぎ、宜しく研精すべし。……ただ、宗廟(祖先)の祀(まつり)を絶たざるは、宜しく太子の徳に在るべし。……不孝の甚しきは祀を絶つに如かず。慎まざるべけんや恐れざるべけんや……」
すなわち、「皇胤一統」(万世一系)のわが国では、革命など生じないと楽観しているのは間違いであって、もし賢聖の主(天皇)がいなければ、数年後に内乱の起こる恐れもあるから、特に次代を担う皇太子は学問(儒学)に精励すべきであり、また「宗廟の祀」(祖先祭祀)の継承こそ最も重要だ、と訓誡しておられるのである。
これはまさに帝王学の要諦といえよう。今上陛下も40年前の昭和57年(1982)、学習院大学ご卒業の際、「花園天皇は……徳を積むためには学問をしなければならないと説いておられ、……その言葉にも非常に深い感銘を覚えます」と語られたことがある。このような深い御遺誡が、末永く承け継がれて行くことを信じ念じてやまない。
補注 史料の検討と再評価が進む 花園天皇をはじめとする持明院統の天皇
鎌倉時代末期から南北朝時代・室町時代については、近年、混乱の中で新しい社会秩序を構築していった時代であり、その中で、大覚寺統=南朝、持明院統=北朝を問わず、皇室が大きな役割を果たしていたことが指摘されている。その視点から、新田一郎『日本の歴史11 太平記の時代』(講談社→講談社学術文庫)、河内祥輔・新田一郎『天皇の歴史4 天皇と中世の武家』(講談社→講談社学術文庫)があり、また特に持明院統・北朝を中心とする京都の朝廷の個別研究として、久水俊和『中世天皇制の作法と律令制の残像』(八木書店)、石原比伊呂『北朝の天皇-「室町幕府に翻弄された皇統」の実像』 (中公新書)がある。
花園天皇については、その伝記として岩橋小弥太『人物叢書 花園天皇』(吉川弘文館)のほか、伝存の御日記について、村田正志編 『和訳 花園天皇宸記』全4巻(続群書類従完成会)、同編『花園天皇遺芳』(楊岐寺)があったが、最近では花園天皇日記研究会『花園天皇日記 (花園院宸記)』 訓読と注釈』(花園大学国際禅学研究所)のほか、同研究所論叢4~10および『京都大学国文学論叢』35に花園天皇日記研究会による「花園天皇日記(花園院宸記)」の「訓読と註釈」が掲載されている。また坂口太郎・芳澤元「花園天皇関係史料・研究文献目録稿」『花園大学国際禅学研究所論叢』2号も参考になる。
花園天皇の著作『誡太子書』について、その解説と書き下しは、所功「帝王学の真髄 『誡太子書』に学ぶ」(『表現者 クライテリオン』24号)に掲載されている。(久禮旦雄)
花園大学国際禅学研究所ホームページ 研究論集『花園大学国際禅学研究所論叢』(全文オンライン掲載)
http://iriz.hanazono.ac.jp/newhomepage/ronsou/index.html
花園天皇日記研究会「『花園天皇日記(花園院宸記)』正和二年六月記―訓読と注釈―」『京都大学国文学論叢』35(オンライン公開)
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/210386