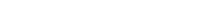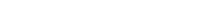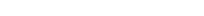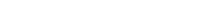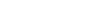朝廷主導の皇威を回復された孝明天皇
所 功
「大政委任論」と「宝暦・明和事件」
江戸時代の朝幕(公武)関係は、初めの厳しさが次第に和らいだ。それにつれて、朝廷の意向を幕府で容認し、むしろ積極的に援助する事例も出てくる。
例えば、前述のとおり、貞享4年(1687)、霊元上皇(112代)の熱心なはたらきかけによって大嘗祭が再興された(本格的な復活は50年後)。また、宝永7年(1710)、新井白石(1657~1725)の奏請によって、中御門天皇(114代)の弟君直仁親王(1704~53)が閑院宮家を創設された(その直孫が光格天皇)。さらに、寛政2年(1790)、老中松平定信の尽力により、京都御所が王朝風に復元されている(それを安政の焼亡後に再建したのが、現存の御所である)。
このうち、新井白石には「我この国に生れて、皇恩に報ひ」る志があった(『折たく柴の記』)。しかも松平定信(将軍吉宗の孫、1759~1829)は、将軍家斉に対して「六十余州は、禁廷より御預かり遊ばされ候御事に御座候へば、かりそめにも御自身の物に思し召すまじき御事に御座候」と諭したことがある。そして国学者の本居宣長(1730~1801)『玉くしげ』と同じく、「大政」(国家の政治)は「朝廷の御任(よさし)」により幕府が預かっているのだから、将軍も自分勝手にできないのだ、という「大政委任論」を表明している。
とはいえ、白石も定信も、当然のことながら将軍・幕府こそ最も重要であり、その名誉・権威の源泉として天皇を敬い朝廷を助けるにすぎない。それゆえ、幕府に批判的な言動には、厳しく目を光らせ弾圧を強行することも少なくなかった。その深刻な代表例が「宝暦・明和事件」である。
すなわち、すでに霊元天皇も関心を寄せられた山崎闇斎(1619~82)の「垂加(すいか)神道」を、その門流の竹内式部(1713~67、徳大寺実憲の近習)が塾で公家たちに講じた。その際に、式部は天皇が学に励み徳を積まれるならば「天下の万民……天子に心を寄せ……将軍も天下の政統を返上せられ候様に相成り候儀は必定」と説いたという。
しかも、その学説を侍読伏原宣条(1720~91、明経博士)からの進講で聴かれた桃園天皇(116代)は、大いに感銘された。のみならず、「それ神道は……万世の為に心をあはせ、天地自然の道……政をとる人、必ず学ぶべき能みち」だから、続けて受講をしたいと希望された。
しかしながら、それが幕府に知れることを恐れた関白たちは、宝暦7年(1757)式部に考えの近い公家を処分し、翌年、式部を追放している。そのうえ、まもなく明和4年(1767)、同じ門流の山県大貳(1725~67)が謀叛の疑いを受けた際に、式部も捕えらられて八丈島へ流罪となり病没している。
ただ、それが世間に伝わると、かえって幕府への批判が高まった。しかも、寛政前後から近海に出没する「異国船」に動揺し右往左往する幕府への不信も強まる。それらが朝廷への期待を促すことにもなったのである。
民の救済と国の独立確保を幕府に要請
幕末の歴代は、光格天皇(在位37年半)から仁孝天皇(在位29年弱)を経て孝明天皇へと直系継承されている。
このうち、光格天皇(1771~1840)は、前号に少し触れたことであるが、天明7年(1787)大飢饉の際(17歳)、御所へ救いを求めてきた窮民たちのために、後見の後桜町上皇(48歳)が施(ほどこし)をされるのと符節を合せて、天皇(17歳)は関白鷹司輔平(49歳)を呼び武家伝奏から京都所司に次のような要請をしておられる。
すなわち『油小路隆前卿伝奏記』(宮内庁書陵部蔵)によれば、「世上困窮し飢渇死亡の者数多」を「甚だ不憫に思し召され、毎々御沙汰」されるだけでなく、「関東(幕府)より救ひ米など差し出され」るよう「再三命ぜら」れたという。
これは、江戸時代に前例のないことであるが、幕府では朝廷の申し入れに応じて、合計1500石の「救ひ米」を出している。しかも、これ以降、幕府では朝廷の意向受け入れるようになり、やがて内政にも外交にも朝廷の諒解「勅許」が必要となったのである。
なお、「光格」天皇以下三代の称号は、平安前期の「光孝」天皇(887年)まであった諡号(御治績を讚美して崩御後に贈る称号)であり、それは仁孝天皇が父帝のため約950年ぶりに復活されたものである(宇多院から後桃園院までの称号は、院御所や陵地などに因む追号であり、明治以降は、一世一元の年号による追号)。
その孫の孝明天皇は、天保2年(1831)6月、仁孝天皇(1800~46)と側室正親町雅子(最後の女院)の間に誕生された。数え10歳で皇太子に立てられ、弘化3年(1846)2月、父帝の崩御により践祚(16歳)、在位21年に及んだ。
この時期は、まさに内憂外患交々来り、亡国の危機にあった、というも過言ではない。たとえば、天保8年(1837)には、大坂町奉行与力を勤める大塩平八郎(1793~1837)らが「救民」のため反乱を起こして、各地で幕政・藩政への一揆が頻発した。また、同13年にはアヘン戦争を仕掛けたイギリスが清国の香港を植民地化しており、そのような外圧が日本にも迫っていたのである。
そこで、孝明天皇は、すでに即位前(弘化2年)、海辺防備を厳しくするよう幕府に申し入れられた。ついで、嘉永6年(1853)アメリカの提督ペリー(1794~1858)が軍艦で来航し幕府に開国を迫ると、伊勢神宮以下の七社と仁和寺以下の七寺に「四海静謐……万民和楽」を祈らしめられた。さらに安政5年(1858)日米修好通商条約の勅許を求めてきた老中堀田正睦(1810~64)の奏請を退けるなど、積極的に“攘夷”の姿勢を示しておられる。それは外国勢力による日本の植民地化を阻止し、ぜひとも独立を確保しなければならない、という固い御信念の表れであろう。
しかし、大老に就任した井伊直弼(1815~60)は、勅許を待たず条約の締結に踏み切ってしまった。しかも、彼に反対する公家(三条実万など)を追放し志士(吉田松陰など)を次々と処刑している(安政の大獄)。それに対して、各地の攘夷論者たちが、幕府を公然と非難し始め、その打倒さえ叫ぶに至ったのである。
皇妹和宮の降嫁による公武一和
ところが、孝明天皇は一方で攘夷を強く主張し続けながら、他方で大政を委任している幕府との協調も念じておられた。この難局に朝廷(公家)と幕府(武家)が抗争していれば、外国勢力に漁夫の利を占められる恐れがあることも、十分認識されていたからであろう。
そこに浮かび上がってきたのが、皇女和宮(1846~77)を将軍家茂(1846~66)に降嫁せしめて“公武一和”をはかる計画である。この案は、初め関白九条尚忠(1798~1871)の家臣が大老井伊直弼の腹臣に伝えたものだが、まもなく大老の横死により権威の失堕した幕府では、老中安藤信正(1819~71)らが朝廷に強く要請してきた。
万延元年(1860)当時、皇族には孝明天皇(30歳)とは腹違いであるが、姉の敏宮淑子内親王(32歳)と和宮親子内親王(15歳)がおられた。しかし、敏宮は桂宮家(皇弟節仁親王が継嗣直後に夭逝し、当主を長らく欠いていた)を相続する予定であったから、家茂と同齢の和宮に降嫁を求められたのである。
それに対して兄君の天皇は、和宮が数年前に有栖川宮熾仁(たるひと)親王(1835~95)と婚約していることなどを理由に、一旦断られた。しかし、侍従岩倉具視(1825~82)らに説得され、やむなく聴許しておられる。その結果、翌文久元年(1861)10月、和宮は江戸に下向したのである。それから5年後に家茂は急逝するが、和宮はその後も朝幕対決の回避に尽力している。
このように孝明天皇は、公武一致して攘夷貫徹をはかるため、苦心を重ねられた。翌文久2年(1864)6月には、一橋慶喜(1837~1913)を将軍家茂の後見職とするようにとの勅旨を降しておられる。
また翌3年3月には、上京した将軍や後見職らを率いて、下鴨・上賀茂社へ(4月、石清水八幡宮にも)行幸祈願された。これは、大政の主導権が将軍(幕府)から天皇(朝廷)に移ったことを、天下の人々に知らしめる画期的な意味をもっている。
それから数年の政局も激動を極めたが、天皇は毅然たる態度を貫かれた。ところが慶応2年(1866)12月、流行の痘瘡に罹り、36歳の生涯を終えられたのである。
その側室中山慶子(明治天皇生母)から実父の忠能(1809~88)にあてた書簡の中で、「(天皇)御二十歳頃より天下擾掛、一日一夜、御安心さまの御閑もあらせられず、実に実に御苦慮のみにあらせられ……」と述懐している。
【補注】幕末維新における孝明天皇の役割
孝明天皇に至る皇室の権威の向上については、藤田覚「幕末の天皇」(講談社選書メチエ→講談社学術文庫)、佐々木克『幕末の天皇・明治の天皇』(講談社学術文庫)、同様の視点で江戸時代全体を論じた藤田覚『天皇の歴史6 江戸時代の天皇』(講談社→講談社学術文庫)がある。
とくに幕末維新における孝明天皇の役割については、家近良樹 『孝明天皇と「一会桑」』(文春新書→『江戸幕府崩壊』と改題して講談社学術文庫)、孝明天皇の前半生を描いた同『幕末の朝廷 若き孝明帝と鷹司関白』(中公叢書)がある。
また儀礼の立場から、幕末の孝明天皇と将軍との関係を論じたのにジョン・ブリーン『儀礼と権力 天皇の明治維新』(平凡社選書→法蔵館文庫)がある。安政の内裏焼亡と復興については五十嵐公一・武田庸二郎・江口恒明『天皇の美術史5 江戸時代後期 朝廷権威の復興と京都画壇』(吉川弘文館)で言及されている。
さらに図録として、松平乗昌監修、吉田さち子・大口裕子編『特別展 孝明天皇-光芒残照 明治の御代へ』(霞会館)、『皇女和宮 幕末の朝廷と幕府』(江戸東京博物館)がある。
なお、明治以降の皇室と徳川家の関係については、高松宮宣仁親王妃喜久子『菊と葵のものがたり』(中央公論新社→中公文庫)が参考になる。