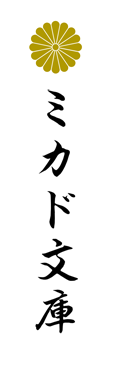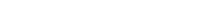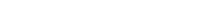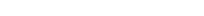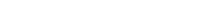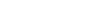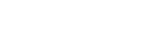三勅祭
さんちょくさい
勅祭とは、天皇陛下の思し召しにより勅使が差遣され奉幣が行われる祭祀である。数多い勅祭のうち、戦後(現在)は、賀茂別雷神社(上賀茂神社)・賀茂御祖神社(下鴨神社)の賀茂祭(5月15日)と、石清水八幡宮の石清水祭(9月15日)、春日大社の春日祭(3月13日)の3つは、特に「三勅祭」と称される。
賀茂・石清水・春日の3社は、それぞれ朝廷より特別の尊崇を受けてきた名社である。ただ、右の3社以外にも例祭に勅使の派遣される勅祭社が16社ある。
そのうち、伊勢の神宮は別格であり、9月の神嘗祭と6月・12月の月次祭など、年に5回勅使が差遣されている。また、例えば九州の宇佐神宮には10年ごとに奉幣が行われている。
【コラム】賀茂祭(葵祭)
三勅祭の1つである賀茂祭は、一般に「葵祭」とも称される。5月15日に京都御所から下鴨神社と上賀茂神社へ一大行列が向かう。
賀茂祭は、欽明天皇の御代(6世紀中頃)に始まったとされる。平安前期(9世紀初頭)から勅祭となり、斎王の参向列も加わった。
本祭は、応仁の乱以後、中絶状態となった(ただし、社頭における祭典は励行された)。やがて、江戸時代に朝廷の儀式や神社の祭儀などを復興しようという動きが出て、熱心な神職らが朝廷や幕府に働きかけ、元禄7年(1694)、約200年ぶりに再興されている。
(G)
【参考文献】(敬称略)
・所功著『京都の三大祭』(角川学芸出版、平成8年)、同著『天皇の「まつりごと」―象徴としての祭祀と公務』(日本放送出版協会、平成21年)、同編著『光格天皇関係絵図集成』(国書刊行会、令和2年)
・皇室事典編集委員会編『皇室事典 令和版』(KADOKAWA、令和元年)