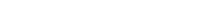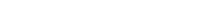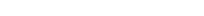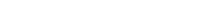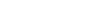吉野と京都の両朝合体と後南朝・伏見宮の消長
所 功
六十年近い南朝と北朝の対立
第96代の後醍醐天皇は、二度の失敗にも屈せず「建武中興」を成し遂げられた。しかし、建武2年(1335)、足利高氏(尊氏)が叛旗を翻し、翌年(延元元年)8月に「朝敵」の汚名を避けるため、持明院統の豊仁親王(光厳上皇の弟)を擁立して光明天皇とした。そのため、後醍醐天皇は三種の神器を奉じて大和の吉野へ遷られたのである。
こうして朝廷は吉野の南朝と京都の北朝に分立し、同じ日本国内に二人の天皇が並立する異例の事態になった。とはいえ、皇位の正統性を象徴する三種の神器は吉野にあった。それゆえ、4年後の延元4年(1339)8月に、後醍醐天皇の崩御により践祚された後村上天皇は30年、ついで後継の嫡長子長慶天皇が16年、さらに同次子の後亀山天皇が9年、合計60年近くも吉野を拠点にしながら、北朝・幕府と対決し続けられたのであろう。
それに対して、北朝を奉じて幕府を開いた足利氏は、みずからの正当性を権威づけるために、なんとか三種の神器を京都へ取り戻そうと躍起になっている。例えば、正平3年=貞和4年(1348)正月、楠木正行たちが四条畷で戦死すると、高師直らが吉野を襲撃し、御所や仏閣を焼き払った。しかし、このときは後村上天皇も側近も事前に神器を奉じて難を逃れることができた。
しかも、まもなく足利氏の身内で抗争を生じ、正平6年=観応3年(1351)、高氏(尊氏)は嫡子の義詮と共に、敵対する実弟の直義や庶子の直冬との戦いで窮地に陥ると、便宜的に南朝へ帰順して、北朝の崇光天皇(光明上皇々子)も皇太弟直仁親王も廃止した。その結果、南朝の天下となり、年号も正平のみとなったので、これを「正平一統」という。
しかし、それも束の間(翌年)、高氏は直義を討つと、後光厳天皇(光厳天皇の皇子)を擁立して北朝を再建した。それに対して、直冬が南朝に帰順し、楠木正儀らと京都を攻めたので、後光厳天皇は美濃や近江の行宮(あんぐう)を転々とされ、ようやく文和4年=正平10年(1355)京都へ戻っておられる。
南北朝「御合体」の条件と結末
それ以降、軍事的に優勢の幕府側は、南朝に何度も「和睦」と称して降服を求めた。けれども、後村上天皇も次の長慶天皇も、頑として応じられなかった。しかし、次の後亀山天皇朝には和平交渉が進められ、元中9年=明徳3年(1392)10月、将軍足利義満から南朝に次のような「御合体」の三条件が示された(『近衛家文書』)。
1 三種の神器、帰座あるべきの上は、御譲国の儀式たるべき旨、その意を得候ふ。
2 今より以後、両朝御流相代の御譲位、治定せしめ候ひぬ。
3 諸国の国衙(領)悉く皆御計ひたるべく候ふ。
すなわち、1まず皇位に不可欠な三種の神器は、南朝の天皇から北朝に対し、譲位の儀式で引き渡されること、2ついで今後の皇位継承は、大覚寺統と持明院統の両流を代々交互に立てること、3さらに諸国の国衙領は、すべて南朝(大覚寺統)の所管にすること、という南朝側に受け入れやすい条件である。
これを承諾された第99代の後亀山天皇は、神器を奉じて吉野から京都に入られ、その神器を後小松天皇が土御門内裏で受け取られた。ところが、義満は約束に反して、まず「御譲国の儀式」を行わず、また大覚寺統の皇子を皇嗣に立てることも行わず、さらに国衙領を旧南朝方に領知させることも行わず、ほとんど裏切ったことになる。
そのため、立腹された後亀山上皇は、応永17年(1410)京都を出奔して吉野に籠られた。それによって2に基づき南朝方皇子の立太子を訴えようとされたのであろう。しかし、同19年、後小松天皇の譲位後、その嫡子が第101代の称光天皇として践祚されるに及び、同23年、上皇は失意のうちに京都の嵯峨御所へ戻っておられる。
「後南朝」の皇胤と神璽の行方
これで南朝は歴史上から消えたかといえば、必ずしもそうではない。後亀山上皇の嫡子とみられる恒敦=良泰親王は、父君と共に嵯峨の小倉山に隠棲していたので「小倉宮」と称されたが、義満の違約により立太子も叶わず薨じた。
しかし、後亀山上皇の嫡男「南方小倉宮聖承」と子息教尊については、内大臣万里小路時房の『建内記』嘉吉3年(1443)5月9日条に「後醍醐院の玄孫、後村上院の曾孫、後亀山院の御孫、故恒敦宮(小倉宮)の御子、去る正長の比、勢州に出奔す。懇望に依り帰京の後、子息(教尊)をもって普広院(足利義教)の御猶子と為し、勧修寺門跡に入室せしむ。その身も得度して法名聖承と云ふ」と記されている。
この伊勢出奔とは、足利氏の内紛で将軍不在中の正長元年(1428)7月に、皇子のない称光天皇(28歳)が病床につかれると、幕府が再び2の約束に反して北朝傍流の伏見宮彦仁王(後花園天皇)を立てるに及び、それに憤慨した小倉宮が、すでに15年前(応永22年)幕府に抗して兵を挙げたことのある伊勢国司の北畠満雅(親房の曾孫)を頼り、下向したのである。
そこで小倉宮は、半年後に満雅が敗死してからも2年近くも抗戦を続けた。けれども、結局、室町幕府の懇望に応じて京都へ戻り、子息の教尊王を将軍義教の猶子(養子)として勧修寺に入れ、自身も出家して聖承と称し、皇位への望みを断つに至ったのである。
しかし、それ以降も「後南朝」勢力と幕府側との攻防が続いた。とくに嘉吉3年(1443)南朝の遺臣日野有光らが御所(土御門内裏)に潜入して「神璽」(勾玉)などを奪い去り、吉野の奥に隠したが、ついで長禄元年(1457)それを赤松氏の旧臣らが奪い返している。さらに、応仁・文明の乱の最中(1470)、西軍の山名宗全は、小倉宮流の「南帝」を擁立して、後花園天皇を奉ずる将軍義政に対抗しようとしたが、3年後、宗全の急逝により幻に終わった(森茂暁氏『闇の歴史 後南朝』角川選書・『南朝全史』講談社選書参照)。
「伏見宮」家の創立とその後裔
一方、北朝側の皇位は、崇光天皇から同母弟の後光厳天皇へと継がれたので、その次には持明院統の正嫡として前帝の嫡男栄仁親王を立てられると思われた。しかし、当帝は幕府の支持を得て、自分の皇子緒仁親王に譲位し後円融天皇とされ、その後も後小松天皇から称光天皇へと継承されていった。
そこで、栄仁親王も嫡男貞成王も皇位には即けなくなった。しかし、その代わりに伏見御領などを伝領して「伏見宮」と称した。しかも、前述のごとく皇子のない称光天皇が病死されると、将軍義教の護持僧満済の周旋により、伏見宮貞成親王の嫡男彦仁王が、後小松上皇の猶子とされた上で後花園天皇となられた。これによって、しばらく崇光上皇と後光厳上皇の両流に分かれ対立気味だった持明院統が一体化し、伏見宮家は皇統の危機を救った宮家として代々親王の宣下を受けて世襲親王家になったのである。
この伏見宮家は、その後に創立された桂宮・有栖川宮・閑院宮の三家と同様、皇統の万一に備えてきたが、当主以外は出家したり臣籍に降っている。しかし、幕末から明治にかけて、皇室を強化するため、伏見宮第16世=第二十代にあたる邦家親王の弟と男子7人を初代とする近代宮家が次々と認められ、やがて11宮家になった。けれども、戦後GHQの皇室弱体化政策により、昭和天皇の直宮3家以外、伏見宮の後裔11宮家は、すべて皇籍離脱(臣籍降下)を余儀なくされたのである。ただ、その旧宮家も、いわゆる男系男子による相続が過半で困難になっている。
【補注】 苦難の史実の検証が進む南北朝・室町時代の皇室史研究
南北朝時代から室町時代にかけての皇室の歴史については、特に大覚寺統・南朝の歴史を中心に、多くの研究が蓄積されてきた。近年のものに限っても森茂暁『南朝全史―大覚寺統から後南朝へ』(講談社選書メチエ→講談社学術文庫)、日本史史料研究会監修・呉座勇一編『南朝研究の最前線 ここまでわかった「建武政権」から後南朝まで』(洋泉社歴史新書y→朝日文庫)がある。また同時代の通史である新田一郎『日本の歴史11 太平記の時代』(講談社→講談社学術文庫)、桜井英治『日本の歴史12 室町人の精神』(同)も皇室の動向についての記述が多い。
後南朝については、瀧川政次郎博士を中心に刊行された後南朝史編纂会『後南朝史論集 吉野皇子五百年忌記念』(新樹社→原書房)があり、最近では森茂暁『闇の歴史、後南朝 後醍醐流の抵抗と終焉』(角川ソフィア文庫)、後南朝を中心とした禁闕の変・長禄の変について述べた渡邊大門 『奪われた「三種の神器」 皇位継承の中世史』(講談社現代新書→草思社文庫)がある。それらの研究成果を読みやすくまとめたものとして『歴史読本』平成19年7月号「検証 後南朝秘録』(新人物往来社)が参考になる。
持明院統・北朝の天皇については、政治的動向については石原比伊呂『北朝の天皇-「室町幕府に翻弄された皇統」の実像』 (中公新書)、美術史における業績については髙岸輝・黒田智『天皇の美術史3 乱世の王権と美術戦略』(吉川弘文館)のほか、個別の伝記として飯倉晴武 『地獄を二度も見た天皇 光厳院』(吉川弘文館)、深津睦夫『光厳天皇 をさまらぬ世のための身ぞうれはしき』(ミネルヴァ書房・人物評伝選)がある。
伏見宮家の成立については、『歴史読本』平成18年11月号「天皇家と宮家」(新人物往来社)をもとにした所功編著『日本の宮家と女性宮家』(新人物往来社)に詳しい。また個別の伝記としては、後花園天皇の父君である伏見宮貞成親王(後崇光院)についての横井清 『室町時代の一皇族の生涯 『看聞日記』の世界』(そしえて→講談社学術文庫)がある。(久禮旦雄)